近年の特徴は、課程別割合において博士課程に占める奨学生の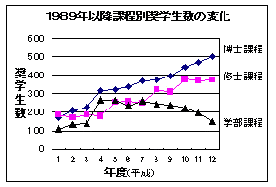 割合が高くなった点です。その推移は、1989(平成1)年度以降の課程別分布(右のグラフ参照)が示すとおりです。これは、米山奨学事業の目的である「優秀性」を求める要素の一つの表れと考えられます。今後は、この優秀性の他に「コミュニケーション能力・異文化理解・地域ボランティア活動への参加」などを含め、米山奨学生としてふさわしく、また、ロータリアンが期待する奨学生をいかに見いだすかが課題となります。
割合が高くなった点です。その推移は、1989(平成1)年度以降の課程別分布(右のグラフ参照)が示すとおりです。これは、米山奨学事業の目的である「優秀性」を求める要素の一つの表れと考えられます。今後は、この優秀性の他に「コミュニケーション能力・異文化理解・地域ボランティア活動への参加」などを含め、米山奨学生としてふさわしく、また、ロータリアンが期待する奨学生をいかに見いだすかが課題となります。
| 2001学年度 米山奨学生1,000人の内訳 |
| 種 類 | 対象者 | 選考 | 奨学生数 | ||
| 米山奨学金 | YU | 学部課程 | 各地区選考委員会 | 128 | 925 |
| YM | 修士課程 | 325 | |||
| YD | 博士課程 | 472 | |||
| 特別米山奨学金 | SY−1 | 農業研修 | 15 | ||
| SY−A | 上級研究者 | 学務委員会 | 10 | ||
| SY−S | 博士号取得の元米山奨学生 | 10 | |||
| CY | YD最終学年 | 40 | |||
| 合 計 | 1,000 | ||||
ポスト2000年の留学生政策(1999年3月文部科学省発表)でうたわれている中に「世界に開かれた留学制度の構築 − 渡日前入学の普及」があります。この渡日前入学普及のために現行の「日本語能力試験」と「私費外国人留学生統一試験」を一本化し、あらたな試験として「日本留学試験」が2002年度から実施されます。
このような留学生受入れ事情の変化の中で、米山奨学会は広く優秀な留学生を発掘する採用システムの導入として日本以外の国で募集し選考する制度「SY−A奨学金」を2000年度から試行しました。現行は、募集対象を韓国・台湾とし、両学友会(元米山奨学生の交流・友好を深める組織)選考委員会にその募集と選考を委託しています。2000年度は第一期生として両学友会から3名ずつ、計6名の研究者を招へいしました。韓国学友会選考による3名の研究者は昨年7月に入国し、台湾学友会選考による3名の研究者が昨年12月および1月に入国しました。【ハイライトよねやま3(2000年8月1日発行)にて韓国学友会選考による3名の研究者を紹介済み】
◆ SY−A奨学金の特長
前述のとおり、特長は日本以外の国で募集し選考するという新しい選考システム「渡日前採用」にあります。奨学期間は7月〜翌年6月までの間の6カ月から12カ月間とし、奨学期間中は世話クラブの例会に毎月1回出席します。応募資格は、博士号の学位をもつ上級研究者で、日本側受入れ大学および指導教員が渡日前受入許可を発行することを合格の条件とします。近年、日本でも英語を公用語とする大学・研究所が増えてきました。そのためSY−A奨学生は日本語能力を合格の条件にしていません。
ただし、日本で生活する以上は日本文化を学ぶという姿勢をもつこと、特に例会参加においては日本語でのコミュニケーションをはかり、ロータリアンの方々との交流に努めることが望まれます。
◆ SY−A奨学生(台湾)との懇談会開催・・・「重要な日本語でのコミュニケーション」
去る月24日(土)にSY−A奨学生(台湾)を対象とした懇談会がホテルニューオータニにて開催されました。*1 出席者は以下のSY−A奨学生とそのカウンセラーおよび2580地区米山奨学委員長・鈴木喬氏(東京江北RC)です。
・ 鄭陸霖さん(東京東江戸川RC/2000年12月来日/中央研究院社会学研究所
(台北市)研究員/東京外国語大学/日本の経済社会学)
・ 鍾起恵さん (東京西北RC/2001年1月来日/世新大学(台北市)副教授/東京大
学/日本の放送文化と台湾)
・ 呉栄杰さん (東京江戸川RC/2001年1月来日/台湾大学(台北市)教授/早稲田大
学/日本の農業金融に関する研究)
・ 藤原龍光氏(東京東江戸川RC・カウンセラー)
・ 鈴木辰男氏(東京西北RC・カウンセラー)
・ 後関和之氏(東京江戸川RC・カウンセラー)
また、当日は台湾学友会「(社)扶輪米山会 *2」 の理事長 許邦福氏(フォーチュンエレクトリック總経理)および常務理事 阮允恭氏(瑞鋼貿易總経理)が来日されていたため同席される運びとなり、「SY−A奨学生を送り出す側」と「受入れる側」、そして「奨学生本人」を迎えての懇談会となりました。
懇談会は宮崎幸雄事務局長の司会進行により、(1)台湾での募集・選考システム (2)SY−A奨学生の受入れ期間と日本語能力 (3)世話クラブ選定の際の留意 (4)世話クラブ・カウンセラーによる受入状況 (5)今後の留意点・改善点 等に関して現況報告とともに活発な意見交換が行われました。ここに懇談会での具体的な意見を紹介します
1. SY−A奨学生の声
(1) 「かつてアメリカに6年間留学したことがあったが、その時よりもこの7カ月の日本留学の方が影響力が大きいと思う。これは、カウンセラーやご家族のおかげである。まるで、家族の一員として生活しているような貴重な体験をしている。
(2) 「世話クラブ・カウンセラー制度は素晴らしいシステムだ。研究では英語を使っているが、ロータリー・クラブ例会では日本語でコミュニケーションをとるよう努力はするが、なかなかうまくいかない」
2. カウンセラーの声
(1) 「ロータリー・クラブや家族の中に英語を話せる人がいるからコミュニケーションはできるとは言え、やはり日本語での交流が重要だ。」
(2) 「クラブでお世話をするのが6カ月では短すぎる・・・なじんだころに帰国という感じだ。せめて1年間の奨学期間は必要だ」
(3) 「SY−A奨学生は博士の学位をもつ上級研究者であり、日本語を得意とせず、奨学期間が短いということから、クラブ会員との交流をもつのが難しいと感じる」
3.「世話クラブの依頼をする際、英語でのコミュニケーションが可能なカンセラーを推薦してもらうようにするが、基本は日本語での交流であることを大切にしたい」 (地区米山奨学委員長)
4.「渡日前に日本語教育をしているが研究者であるSY−A奨学生が台湾で事前に日本語学習の時間を作るのは難しい。また、日本で生活しながら学ぶ日本語が一番役に立つ。この点を考えながら、さらに台湾での事前日本語学習に力を入れたい」(台湾学友会選考委員)
このように、奨学生においては日本でのコミュニケーションに努めようとする気持ちと現実のギャップが感じられ、カウンセラーからは実際に感じている制度への疑問や問題などが具体的に語られるという充実した内容となりました。
SY−A奨学金は、2002年度までの3年間が試行期間ですが、これらの意見やアドバイスを参考に改善を重ね、「日本以外の国で募集・選考をする渡日前採用」という新しい選考システムをさらに充実した制度にしていきたいと考えます。
注)*1 国際ロータリー第2580地区地区大会が2001年3月24日にホテル・ニューオータニで開催された。SY−A奨学生受入れ地区は2580地区であるため、同日・同会場にて懇談会を開催する運びとなった。
*2 台湾において、台湾学友会は(社)扶輪米山会として、1997年に社団法人の認可を取得している。
(栗原)
以上
(財)ロータリー米山記念奨学会
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 abc会館ビル8F
Tel:03-3434-8681 Fax:03-3578-8281
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/